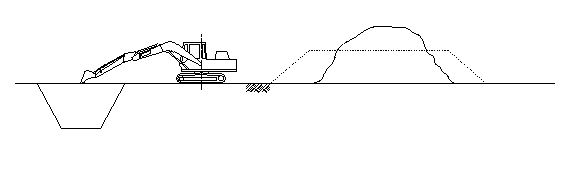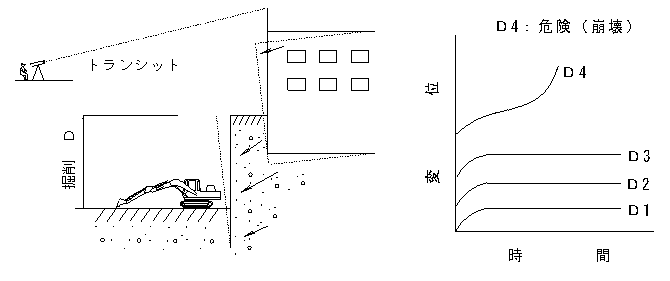
(a) (b)
図-1 (a)掘削地近くのビルの動きをトランシットで察知し、崩壊を未然に防ぐことができた。
(b)掘削深さD4になったとき、変位が加速的に増大した。
切土の考え方
危険性を伴う掘削は、構造物の基礎、地下鉄、トンネル等の工事には必ず施工されなければならない。とくに日本では、土質構成が複雑な上に、地下水が高く、湧水を伴うので一般に難工事になることが多い。
現場の土質、すなわち土のせん断強度、あるいは掘削面積の大小によって差はあるが、地表から数十センチ、ときには数メートルまでの掘削では、掘削壁面は補強なしでそのまま自立が可能である。この深さを自立高さと呼んでいる。しかし掘削がある程度以上深くなると、もはや自立し得なくなり、崩壊することをわれわれは経験で知っている。その崩壊に到達するまでには必ず地盤の変形が発生している。土の応力-変形の関係は、ある程度の変形がすすんだところで最大の抵抗力を発揮し、それらはまた時間の関数であることも知られている。この地盤の変形をとらえて、崩壊を予知しうることがある。
一般にはこの崩壊を防止するための構造物(土留工)が架設されることになるが、この土留工に働く土の圧力が土圧である。土圧は、掘削深さが大きくなるとそれに従って増大するが、土質にも関係し、また地盤の変形、すなわち土留壁の変形量とも大いに関係があることを知らねばならない。土圧の算定を誤ったり、土留工が不十分であれば崩壊が発生することはいうまでもない。
さらに掘削深さが大きくなって地下水面以下に達すると湧水を伴い、あるいは水圧が作用し、土圧プラス水圧が土留壁に作用することになる。
この地下水に関しては、掘削の進行に伴って境界条件が変化するので、その挙動は時々刻々に変化し、その取扱いはきわめて厄介である。掘削においては土圧対策よりもしばしば水圧対策、湧水対策がむずかしく、事故の原因になることも多い。
事故を事前に防止した例
駅前の地下街の建設に際し、軟弱地盤の掘削が行われていた。もちろん設計時には土圧、水圧等の算定が行われ、それをもとに支保工、排水工などの検討が行われたことはいうまでもない。掘削現場近くには警察庁舎などの高層ビルが立ち並ぶ繁華街でもあり、現場の地盤について各種の計測が行われていた。それらに加えて、トランシットで高層ビルの頂部の変位を計測していたのである。最初の間は掘削が進むにつれてビルが数ミリ変位し、掘削を止めるとその変位も停止していた。しかし、ある程度掘削が深くなった時点で、図-1のD4のように掘削を停止しても変位が加速的に増大する徴候をみせたので、急ぎ、対応策を講じて事故を未然に防いだということである。もし、このトランシットによる計測がなされていなかったとしたら、もっと大きな事故に至ったかも知れない。
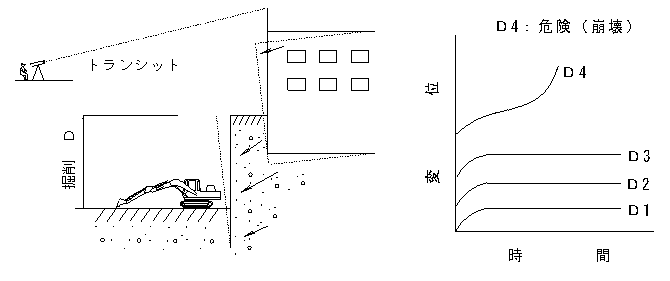
(a) (b)
図-1 (a)掘削地近くのビルの動きをトランシットで察知し、崩壊を未然に防ぐことができた。
(b)掘削深さD4になったとき、変位が加速的に増大した。
情報化施工
土留工の変形について
自立式の場合、山留壁の変形量の許容値が掘削深さの3%までとされています。 (道路土工指針)
よって下図の場合、掘削深さが2mとすると
⊿L=H * 0.03
=2 * 0.03
=0.06m
となりそれを超えると崩壊する危険があると考えること。
この許容変位量を超えないように日々計測を行い、土留工の崩壊を事前に防ぐこと。
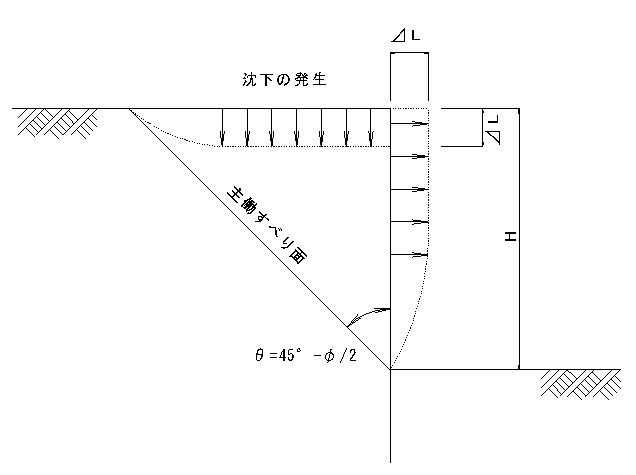
ひずみが増大した場合の対策
1、受働側の処置をする。(掘削面内に注水、土砂の投入等)
2、主働側の対策(危険物の移動、薬注、上載荷重の低減等)
3、その他(本社に連絡し、対策依頼する)
切土法面
下図のような断面の場合、水の流れ面に沿ってすべり、崩壊する可能性がある。
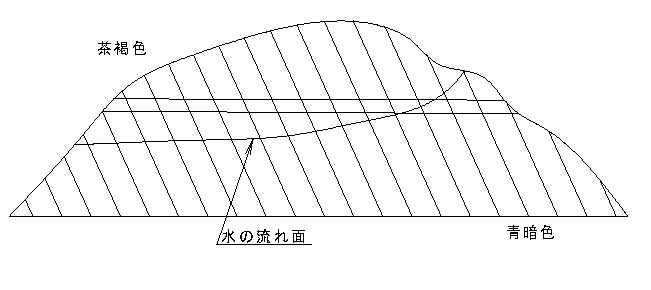
下図のように切土した場合、それまで上載していた土が無くなるため、応力開放し、切土面が膨張する。膨張
することによりテンションクラックが入り、そこから水が入り込む。これによりスベリが誘発され崩壊につながる。
切土面の背面に注意し、クラックの発生がないか観測する。
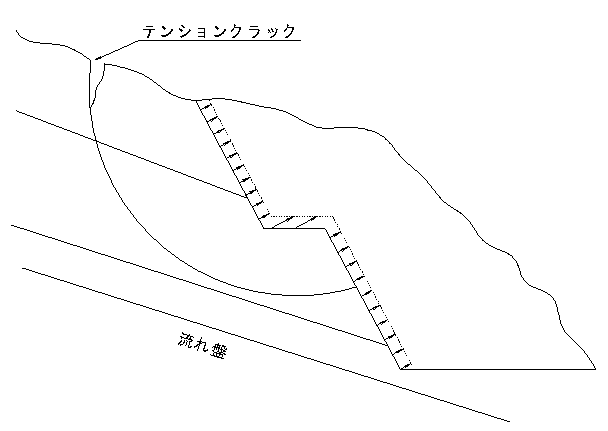
切土した土砂の処理
掘削した土砂は、そのまま放置せず、必ず転圧をし整形すること。雨が降った場合、転圧していないと土砂の内部に水が入り込み、運搬等の時の処理が大変になる。転圧してあれば水が入り込みにくく、処理の際に手間がかからない。土は、水を含むと金がかかります。