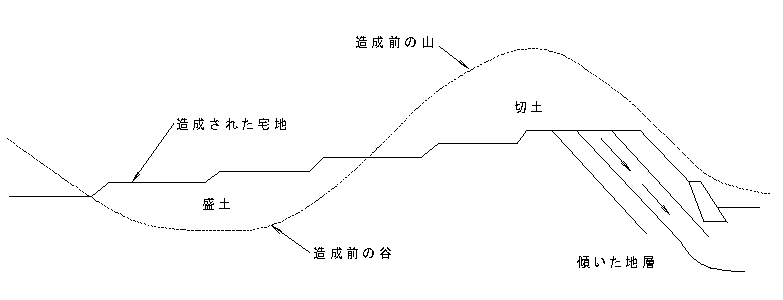
盛土の考え方
最近の造成宅地は丘陵や山麓を切り開いたところが多く、図-1のように山を削りとった後にできる敷地(切土宅地)と削った土を盛り立ててつくった敷地(盛土宅地)とがある。これらを見分けるには宅地面に続く斜面の植生の様子や、宅地周辺の谷や沢の状況などが参考になる。
一般に切土はよく固まった良い地盤、盛土はよく固まっていない悪い地盤と言われるケースが多い。しかし、盛土工事も粗悪な施工を行わず、入念な施工を行えば良質な敷地として利用することができる。一方、切土の敷地もすべてがよいわけではない。図-1の右側部分のように自然の地層は往々にして傾いており、また長年の間に風化してもろくなっているものである。このような所では、地層面に沿って矢印の方向にスベリが起こりがちである。したがって、安全性の面からみて良い宅地か悪い宅地かは、地層の状態、土質、排水状況、工事方法などを総合して判断しなければならない。
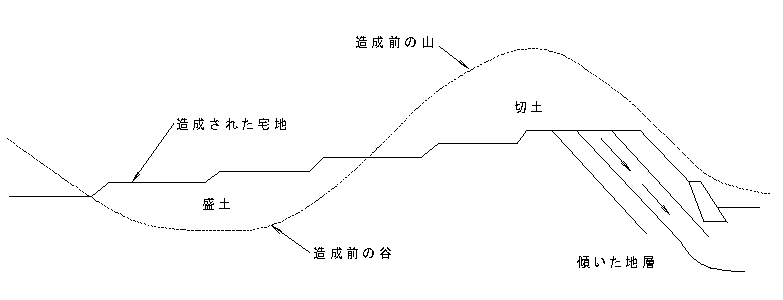
図 - 1 山地部の宅地造成
一般に斜面は自然斜面、切土斜面、盛土斜面にわけられるが、自然斜面と切土斜面の安定性は地質的条件に影響されやすく、盛土斜面の安定性はほとんど人為的条件で決定される。地質的条件としては、いわゆる構造地盤、すなわち図-2に示すような流れ盤構造をもった傾動地盤と著しく破砕を受けた破砕地盤とが重要である。これらの地盤は線構造、面構造が発達して力学的に方向性をもつだけでなく、地下水の移動方向を限定して集中しやすくする。このように斜面安定に影響を与える地質的条件のほかに、地形条件、植生条件および降雨条件が複雑に関連する。
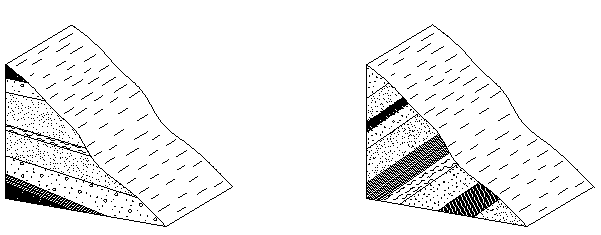
図-2 (a)流れ盤構造 図-2 (b)受け盤構造
斜面の崩壊が起こりやすい。 斜面の崩壊は起こりにくいがかならずしも
安全ではない。
・道路盛土
道路は、堤防などと違ってしゃ水性に神経を使わなくてよいが、車両の通過による繰返し荷重に耐えるよう、また降雨や地震などによって壊れたり変形したりしないような構造が要求される。特に、舗装から伝達される荷重を直接に支える路床部の耐荷性、斜面の安定性、橋・カルバートに接する土工部分、すなわち裏込め部の安定性などは重要である。
橋・カルバートの裏込め部に関する問題点を図-10によって考えてみる。図-10(a)は立体交差する道路のボックスカルバートとその接続部分、(b)は橋台とその接続部分を示している。カルバートや橋台は設計において沈下がきわめて小さくなるような構造となっている。一方、接続する土工部分は盛土の一部であるから、ある程度の沈下をまぬがれない。したがって、工事完了の時点で構造物とその接続部分の表面の舗装が平坦に仕上げられていても、時間の経過とともに両者の沈下量の違いによって表面に段差を生じることになる。
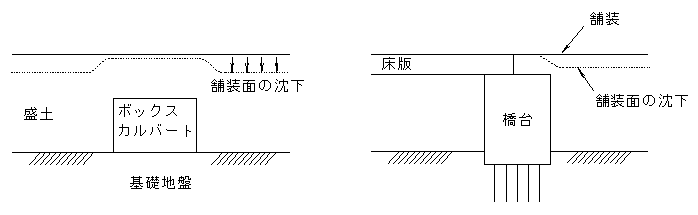
図-10(a)ボックスカルバート構造 図-10(b)橋台構造
構造物はほとんど沈下しないが、接続する土工部分は沈下しやすいので不同沈下のために交通に支障をきたす。
ある道路ではこのような接続部の不連続性のために、自動車が通過する際に運転者が大きいショックを感じるようになったので、アスファルト合材をかぶせて路面を平滑にした。しかし、その後も裏込めは少しずつ沈下を続けるので、あるころあいをみて同じような補修を繰返している。このような補修を多数の地点で実施するのは手間であり、極力少なく補修のないようにしたいものである。そのために図-11のように良質の裏込め材料を使用し、十分に締固めるとともに排水にも留意し、沈下量をできるだけ小さくする。良質の材料とは、粘土・シルトなど微粒子の含有量が25%以下で、砂・レキ(最大100mm)が主体であるような土である。
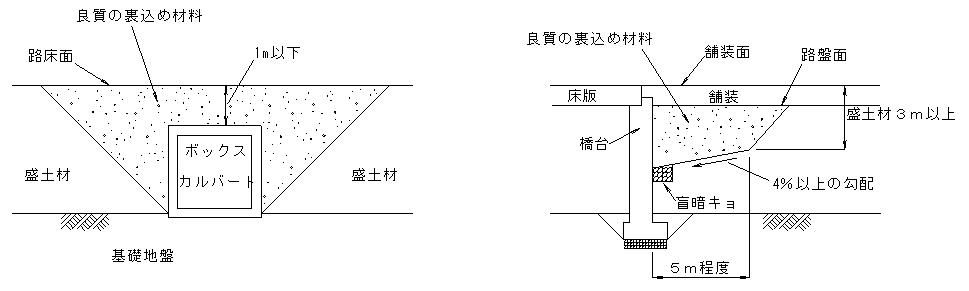
・斜面の安定
工事中および完成直後の斜面は芝や草が十分に育っていないので、いわば裸の状態である。したがって、雨が降ると斜面の表層土は水によって流されやすく、水が流下する方向に水みちができる。いったん水みちができると、降雨のたびごとに流下水はそこに集中し、浸食はますます激しくなる。その結果、雨裂またはガリーに発展して斜面が崩壊することがある。このような表面浸食を防ぐために斜面保護工が行われる。保護工には多くの種類があるが、芝や牧草など植生による工法と石張やクイなど建造物による工法とに大別される。
表面からの浸食による破壊のほかに図-12のように、斜面内部の土塊のバランスが破れて崩壊することがある。この原因についてみると図-13のように、盛土表面と基礎地盤との間の高低差のために斜面の内側の土はある面を境にしてすべり落ちる危険性をたえず秘めている。スベリが起こる面を正確に知ることは困難だが、経験によると図-13の仮想スベリ面のような曲面である。
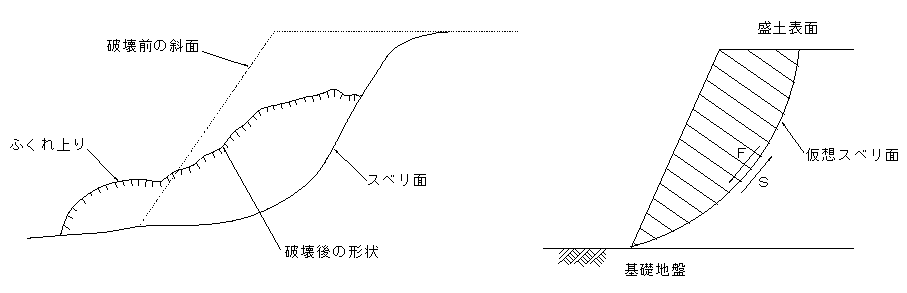
図-12 斜面のスベリ破壊の状況 図-13 斜面のスベリ破壊の説明
スベリを起こす原動力は斜線部の土塊の重量である。重量は鉛直下向きに作用するが、スベリ面においてスベリ方向の成分をもっている。それらの合力がFで表されるものとしよう。一方、このスベリの起動力に対して抵抗しようとする力が存在する。それは土がスベリ面に沿ってセン断されようとする時に発揮される土のセン断抵抗(またはセン断強さ)である。セン断抵抗はセン断の変形が進むにつれて増加し、ある限度つまり最大セン断抵抗Sを超えると破壊を生じる。したがって、起動力Fが最大セン断抵抗Sより小さい場合(F<S)はセン断破壊によるスベリは起こらない。一般に斜面がふだん安定しているのはこのような条件下にあるからである。
しかし、降雨があると雨水は斜面の内部に浸入し、土塊の重量の増加とともにFも増加し、一方、水分がふえるとSは一般に減少するから、上の不等式の符号が変わりF≧Sとなるかも知れない。そのような場合にはスベリが起こることになる。したがって降雨のような悪条件のもとでもなおかつ安全であるような配慮が要求される。
・盛土の施工
盛土斜面(法面)の安定性は調査試験データに基づいた安定計算によって確かめる。しかし、特別の場合を除いて表-1で与えられる標準勾配を採用し、安定計算を省略する。この表を参考にして、現地の地形、地質、気象条件、隣接する物件、斜面保護工の種類、施工法などを考慮した勾配が決定される。なお表-1の勾配の欄については、図-14を参照。
表-1 盛土材料および盛土高に対する法面標準勾配(道路土工指針)
| 盛 土 材 料 | 盛土高(m) | 勾配(割) |
| 粒度分布のよい砂 粒度分布のよいレキ質土 |
0 〜 5 5 〜 15 |
1.5 〜 1.8 1.8 〜 2.0 |
| 粒度分布の悪い砂 | 0 〜 10 | 1.8 〜 2.0 |
| 岩塊、玉石 | 0 〜 10 10 〜 20 |
1.5 〜 1.8 1.8 〜 2.0 |
| 砂質土 かたい粘質土、かたい粘土 |
0 〜 5 5 〜 10 |
1.5 〜 1.8 1.8 〜 2.0 |
| やわらかい粘質土、やわらかい粘土 | 0 〜 5 | 1.8 〜 2.0 |
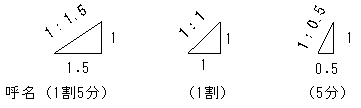
図-14 勾配の表示方法
次に盛土材料を締固める基準を決定する。締固めというのは、土の密度を高めて透水性と圧縮性を低下させるとともに盛土の安定に必要な土の強度を確保する作業である。締固めの程度を規定する方式はいくつかあるが、ここではもっとも一般的に採用されている乾燥密度で規定する方式を説明する。
この方式は、「突固めによる土の締固め試験方法」を基準として、現場で締固めた土の乾燥密度がある値以上になるように規定するものである。まず盛土材料を実験室において規定された試験装置と試験方法によって締固める。材料に適度の水を加えて数種類の含水比をもった試料を準備し、それぞれについて所定の締固めを行った結果を図-15のように表示する。一般に含水比の変化とともに乾燥密度も変化するが、最大乾燥密度が得られる含水比を最適含水比と呼んでいる。以上から理解できるように、高い乾燥密度を得るためには最適含水比またはそれに近い含水比で締固めるのが有利である。盛土の締固め作業においては、材料の含水比調節によって最適含水比付近(±2%)の状態で、最大乾燥密度の90%以上の乾燥密度を確保するのが普通である。
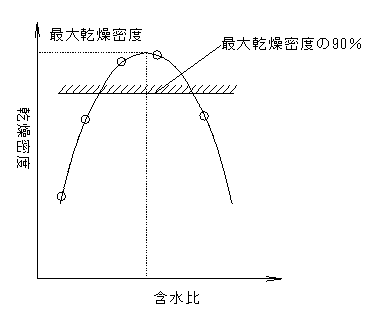
図-15 室内締固め試験結果
現地施工に際しては、まず基礎地盤の排水処理、要すれば良質土との置き換えを行う。傾斜地盤では段切りをして盛土とのなじみをよくする(図-16参照)。
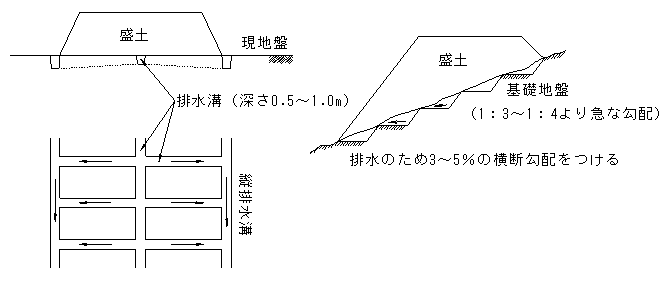
(a) (b)
図-16 基礎地盤の処理例
(a)田畑などの上に盛土するとき、施工しやすくするために素掘りの排水溝により水切りをする。この溝は良質材
料で埋戻してめくら溝とすることもある。
(b)傾斜面上に盛土するとき、盛土と地盤とのなじみをよくしてスベリを防止するために段切りを行う。
盛土材料は約30〜50cm厚さにまき出して、タイヤローラ、振動ローラなどで所定の締固め度が得られるよう転圧する。乾燥密度または間接的な貫入抵抗などの測定を行って施工を管理する。