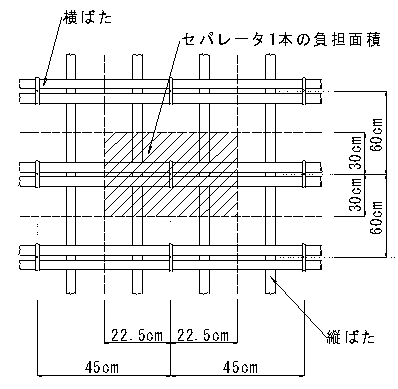型枠の設計
1.型枠の計画
型枠は、建物の構造体を形成するコンクリートを流し込み、所用の形に硬化させるための鋳型である。
そのため、コンクリートが建物の構造主体として要求される各種の条件、たとえば形状、寸法、位置の正確性などを十分に満足しうるように、綿密な考慮を払って計画し、施工されなければならない。
型枠は従来、一般に仮枠と呼ばれて、単なる仮設物のような概念で取扱われることが多かったが、コンクリートの施工段階での型枠が分担する役割はきわめて重要であり、粗雑な型枠工事のためにコンクリートの不均一、はらみ出し、破壊などによって工事全体が不良になることからみても、型枠は本工事と同様、あるいはそれ以上に考える必要がある。
2.型枠の必要条件
型枠工事の実施に当たり、その計画・施工のための必要条件は次の点である。
a)強度
コンクリートの荷重、動荷重などの各種外力に対して必要かつ十分な強度を持ち、変形することのない最小限の堅牢度を有すること。
b)経済性
仮設工事として安価なこと。
c)精度
形状・寸法が正確で、必要な水密性を保有すること。
d)工事の簡易性
加工・組立てが簡単で、取外しが容易であること。
以上4点の必要条件の中で、型枠の計画に当たって見落とされがちなのは経済性の点である。型枠の原価を安くするためには、材料はなるべく市場品から選定し、転用回数を増し、補足・修理の工費をなるべく不要とすることが必要である。
また、型枠材料の寸法が多種類になると市場品の収集に不都合であり、原価が割高となるばかりでなく、整理にも余分の手間を要求することになるから、強度計算上はあくまでも合理的であっても、材種はできるだけ少なくなるように心がける必要がある。
3.型枠計画の方針
a)工法の決定
型枠工法には、通常の構造物に使用されているような一般工法の他にスライディングフォーム工法、トラベリングフォーム工法などの種々の特殊工法もあるので、条件を十分考慮して採用工法の決定を行う。
b)材料の選定
構造物に要求される仕上りの条件、気象条件、作業性、転用回数など検討し、使用材料(木製型枠にするか鋼製型枠にするか、合板などの型枠材料にするか)を選定する。一般的に型枠材料として転用回数の大きい恒久材を用いれば、イニシャルコストは高いが転用回数を考えれば経済的になることが多い。
c)型枠の細部の計画
単位型枠の大きさ、製作場所、安全性および作業性を考慮した組立て・解体の方法、破損、消耗を防ぐための方策などを細部にわたって計画する。
d)型枠の転用計画
型枠工事費を低減するためには、周到な転用計画を行なうのが不可欠の要件である。したがって、工程、構造物の形状、解体時間、転用する場合の作業性などを十分検討し、転用計画を立案する。
以上、4点について型枠計画に当っての主な検討事項を述べてきたが、型枠はコンクリート構造物の形状および施工条件によっては、特殊な型枠構造および工法が有利な場合があるので、計画に当って比較検討の必要がある。たとえば高い橋脚やサイロなどにおいて、大型パネルを用いたスライド式移動型枠、またダムなどでは、クライム式移動型枠がそれぞれ有利になる場合が多い。
また、同一形状の水平方向に長いコンクリート構造物においては、単位の型枠移動および固定する特殊支保工材を併用することによって、有利に分割施工することができる。よって型枠の計画に当っては、コンクリート構造物の形状、工期および施工条件を加味する必要がある。
4.型枠の設計例
設計条件
壁厚 1.5m 、長さ 10.0m 、 リフト高 2.0m の構造物についての型枠の設計を行なう。
型枠の計画
縦ばた、横ばたで合板を受け、フォームタイで緊結する型枠とする
打設計画
1時間当りのポンプ打設量を20m3/h とする。コンクリートの打設温度=20℃ とする。
・コンクリートの側圧
コンクリート標準示方書より側圧の算定には、次式を用いる。
(1)柱の場合
p=7.8 * 10-3 + 0.78R /( T + 20 )≦ 0.15 (N/mm2)
または 2.4 * 10-2 * H
(2)壁の場合でR≦2m/hのとき
p=7.8 * 10-3 + 0.78R /( T + 20 )≦ 0.1 (N/mm2)
または 2.4 * 10-2 * H
(3)壁の場合でR>2m/hのとき
p=7.8 * 10-3 +( 1.18 + 0.245R )/( T + 20 )≦ 0.1(N/mm2)
または 2.4 * 10^-2 * H
ここに、 p:側圧 (N/mm2)
R:打上り速度(m/h)
T:型枠内のコンクリート温度(℃)
H:考えている点より上の、フレッシュコンクリートの高さ(m)
今回の場合の打上り速度は、壁厚 1.5m、幅 10.0mで1時間当りのポンプ打設量 20m3/hであるため
R=20 / ( 1.5 * 10.0 )
=1.33 m/h
よって(2)の式で算出
p1=7.8 * 10 ^-3 + 0.78 * 1.33 / ( 20.0 + 20 )
=0.033(N/mm2)
p2=2.4 * 10^-2 * 2.0
=0.048(N/mm2)
ゆえに
p=0.048 (N/mm2)
・設計計算
型枠の合板、横ばた、縦ばた、フォームタイの関係は、下図に示すとおりである。型枠に作用するコンクリートの圧力は、合板→縦ばた→横ばた→フォームタイの順に伝わる。設計は、この順序で部材の検討を行なう。
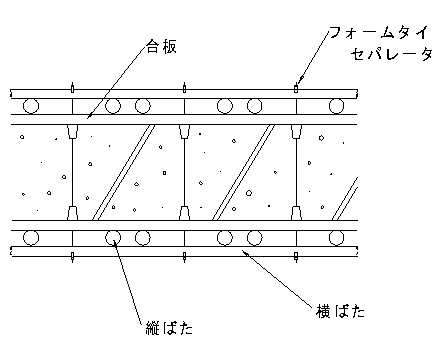
a)合板の検討
合板には型枠用合板(厚さ12mm、900*1800mm)を繊維方向に使用する。
許容曲げ応力度 fb=14 N/mm2
ヤング率 E =5600 N/mm2(厚さ12mmの場合 湿潤状態での値)
合板は、縦ばたにより押さえられているので、合板を検討するということは縦ばた間隔が設定した間隔で良いかどうか検討することである。
合板は、等分布荷重が作用する単純梁(幅b=1cm、高さh=1.2cm)として応力計算を行なう。スパンLは縦ばた間隔でここでは22.5cmとする。
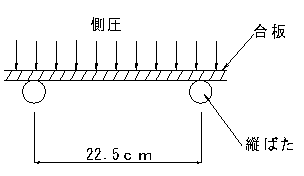
合板を梁と考えた場合の断面性能は公式から
断面二次モーメント
I = bh^3 / 12 = 10 * 12 ^3 / 12 = 1440 mm4
断面係数
Z= bh^2 / 6 = 10 * 12 ^2 / 6 = 240 mm3 となる。
・荷重
合板に作用する単位幅(1mm)当りの荷重wは、コンクリートの最大側圧が0.048N/mm2であったから
w=0.048 * 1
=0.048 N/mm となる。
・曲げに対する検討
最大曲げモーメントMmaxは、次式から求める。
Mmax=w * L^2 / 8
=0.048 * 225^2 / 8
=304N・mm
この最大曲げモーメントから梁に生じる曲げ応力度σbを次式から算出する。
σb=Mmax / Z
=304 / 240
=1.3N/mm2 < 14N/mm2 OK
・たわみに対する検討
許容たわみ量をどの程度におさえるかということは、建物の部位、仕上げの種類により異なるが、一般に0.3cm程度を標準としているので、許容たわみ量0.3cmとする。
たわみを等分布荷重が作用する単純梁の公式から求めると、
δmax= 5 * w * L^4 / ( 384 * E * I )
= 5 * 0.048 * 225^4 / ( 384 * 5600 * 1440 )
= 0.2mm < 3mm OK
b)縦ばたの検討
縦ばた材には、単管φ48.6*2.4を使用する。
断面二次モーメント I = 93200 mm4
断面係数 Z = 3830 mm3
許容曲げ応力度 fb = 240 N/mm2
ヤング率 E = 2.1 * 10^5 N/mm2
縦ばた材を検討するということは、横ばた間隔で縦ばたがOKかどうか検討することである。
縦ばたは、等分布荷重が作用する連続梁として計算してもよいが、ここでは単純梁として応力計算を行なう。
横ばた間隔で L=60cmとする。
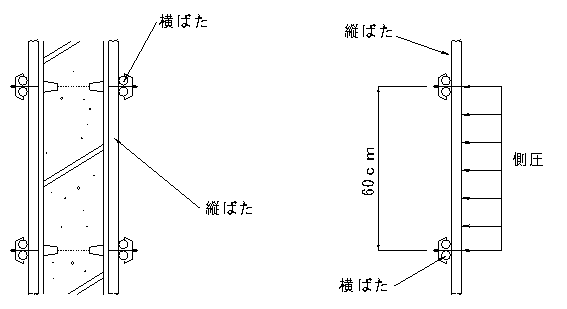
・荷重
縦ばたに作用する荷重wは、縦ばた間隔が225mmであるので
w=0.048 * 225
=10.8 N/mm である。
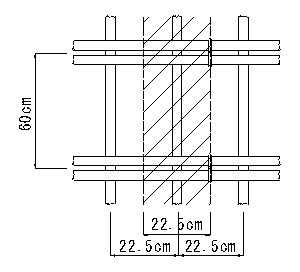
・曲げに対する検討
最大曲げモーメントMmaxは、単純梁の等分布荷重の場合の公式から求める。
Mmax = W * L^2 / 8
= 10.8 * 600^2 / 8
= 486000 N・mm
σb = Mmax / Z
= 486000 / 3830
= 127 N/mm2 < 240 N/mm2 OK
・たわみに対する検討
単純梁の等分布荷重の場合のたわみ公式から
δmax = 5 * w * L^4 / ( 384 * E * I )
= 5 * 10.8 * 600^4 /( 384 * 2.1 * 10^5 * 93200 )
= 0.93mm < 3mm OK
c)横ばたの検討
横ばた材には、単管φ48.6*2.4を2本使用する。
断面二次モーメント I = 93200 mm4
断面係数 Z = 3830 mm3
許容曲げ応力度 fb = 240 N/mm2
ヤング率 E = 2.1 * 10^5 N/mm2
コンクリート側圧は、縦ばた材を通して横ばた材に伝達されるので横ばた材は、縦ばた材との交点で集中荷重を受ける梁として検討するのが実情に近いと思われるが、ここでは等分布荷重を受ける単純梁と仮定して検討を行なう。
スパンLは、セパレータ間隔でここではL=45cmとする。
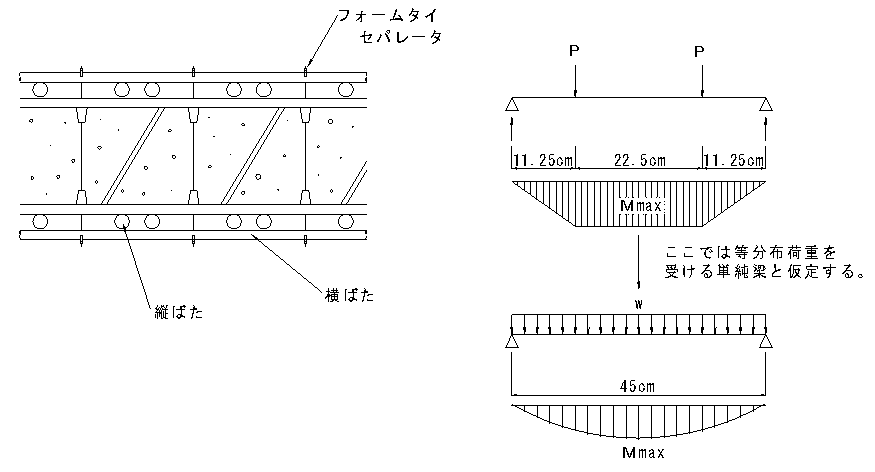 ・荷重
・荷重
横ばた材に作用する荷重wを求めると、横ばた間隔60cmであるので
w = 0.048 * 600
= 29 N/mm となる。
・曲げに対する検討
Mmax = w * L^2 / 8
= 29 * 450^2 / 8
= 734062 N・mm
単管を2本使用するため断面係数Zを2倍する
σb = Mmax / Z
= 734062 / ( 2 * 3830 )
= 96 N/mm2 < 240 N/mm2 OK
・たわみに対する検討
単管を2本使用するため断面二次モーメントIを2倍する
δmax = 5 * w * L^4 / ( 384 * E * I )
= 5 * 29 * 450^4 / ( 384 * 2.1 * 10^5 * 2 * 93200 )
= 0.40mm < 3mm OK
d)セパレータの検討
セパレータは、W5/16(2分5厘)を使用する。
許容引張耐力 Ft = 14000 N / 本
締付け金物には、コンクリート側圧により引張力が生じるが、この引張力が、セパレータの許容引張力Ft以下であるかどうかを検討する。通常セパレータには2分5厘が用いられることが多く、セパレータの引張耐力で横ばた間隔が決まることが多い。
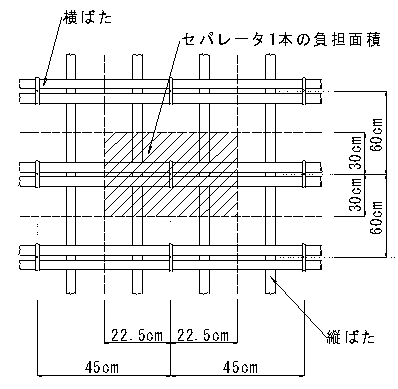
・引張力に対する検討
セパレータ1本に生じる引張力Tは、セパレータ1本が荷重負担する面積Aにコンクリート側圧を乗じて求められるから、セパレータ1本に生じる引張力Tは、
A = ( 225 + 225 ) * ( 300 + 300 )
= 270000 mm2
T = 0.048 * 270000
= 12960 N / 本 < 14000 N / 本
となり、コンクリート側圧に対して現在のセパレータ間隔でOKである。
・伸びに対する検討
セパレータの有効断面積は34mm2であるから、片側の仕上面に影響するセパレータの伸びは、壁厚の半分の長さを用いて、
δmax = T * d * 0.5 / ( E * As )
= 12960 * 1500 * 0.5 / ( 2.1 * 10^5 * 34 )
= 1.4mm < 3mm OK

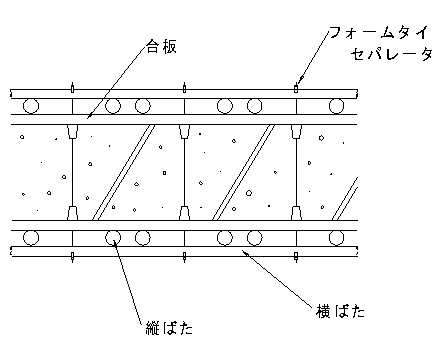
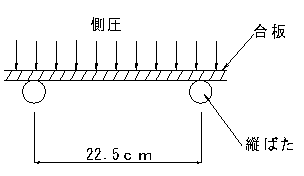
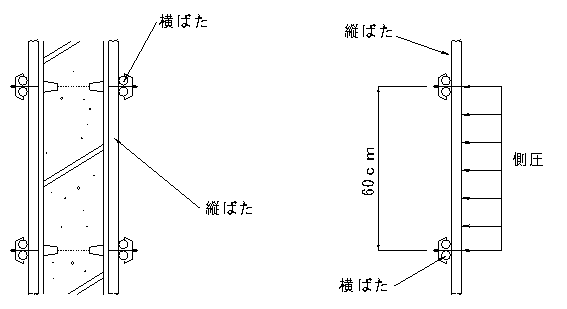
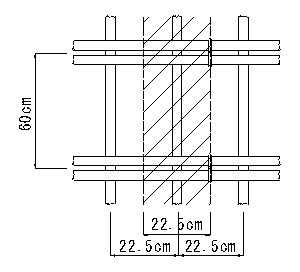
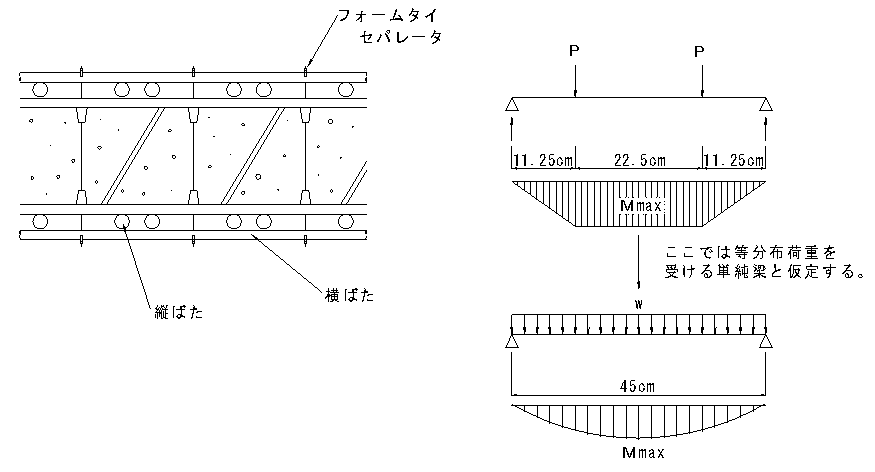 ・荷重
・荷重